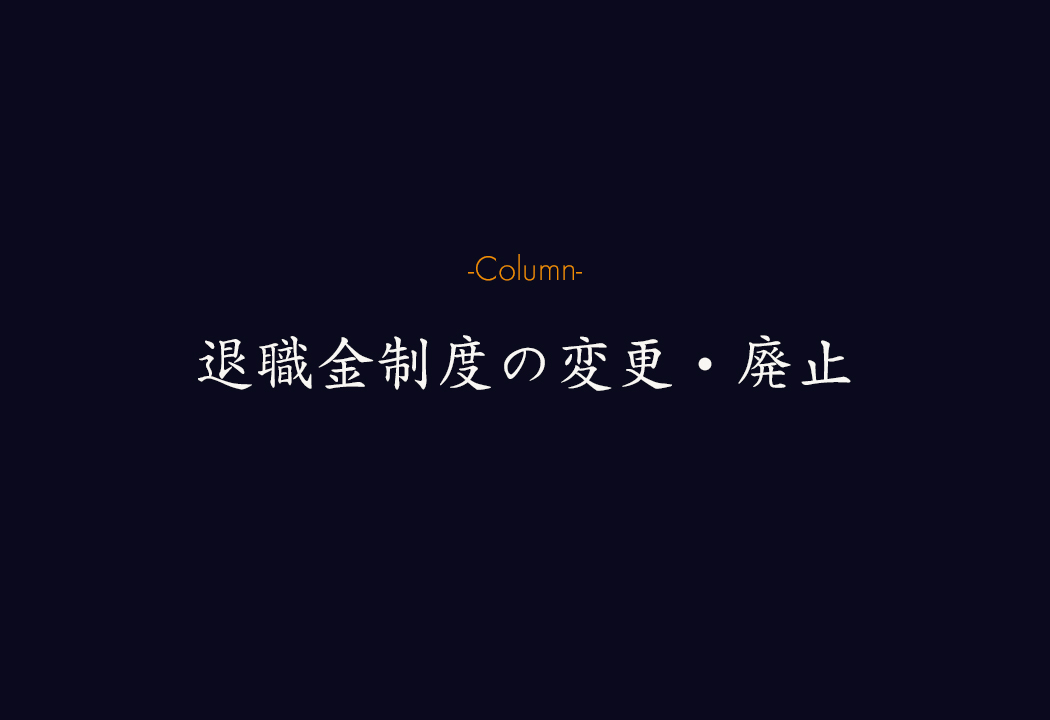こちらの記事もオススメです。
【はじめに】
業績悪化による退職金見直しの現実
「今の業績では、退職金制度を維持するのが正直苦しい」 「経営を立て直すためには、あらゆる固定費を見直さなければならない」
経営者様から、このような切実なご相談をお受けすることがあります。
会社を守り、雇用を守り抜くために、断腸の思いで退職金の見直しを検討されていることとお察しします。
しかし、退職金の減額や廃止は、労働法において「不利益変更」の中でも特にハードルが高い領域です。
進め方を一つ間違えれば、従業員との信頼関係が崩れるだけでなく、法的な紛争に発展し、かえって多額のコストが発生するリスクも孕んでいます。
この記事では退職金制度を見直す際にクリアしなければならない「4つの条件」と、トラブルを避けるための具体的な進め方について、判例を交えて解説します。
【まずは結論】
原則として一方的な減額・廃止は不可
まず、最も重要な結論をお伝えします。
原則として、会社が一方的に退職金を減額したり廃止したりすることはできません。
これは労働契約法により、労働条件を従業員の不利益に変更することが制限されているためです。
変更が法的に有効となるには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
- 従業員一人ひとりから、個別の「真の同意」を得ること
- 変更内容に「合理性」があり、かつ変更後の規則を従業員に「周知」させていること
単に「業績が厳しいから」という理由だけでは認められません。
「倒産を回避するためにはこの手段しかない」 「役員報酬のカットなど、経営側ができる努力はすべてやり尽くした」といった、高い必要性が求められます。
【解説】
退職金の不利益変更が認められる条件とは
1. 「不利益変更」という高い壁
なぜ、退職金の変更はこれほど難しいのでしょうか。
それは、就業規則などで定められた退職金は、恩恵的なものではなく、働いた対価としての「賃金」の一部(賃金の後払い)とみなされるからです。
特に「制度の廃止」は、減額以上にハードルが高く、代わりの措置(給与への上乗せ等)を行わずに会社が一方的に制度を廃止し、それが裁判で認められたケースは確認されていません。
労働契約法第9条では、以下のように定めています。
(労働契約法第9条) 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
実際に、経営難を理由に退職金規定を変更し、支給額を減らそうとしたケースで、会社側の対応が無効とされた裁判例があります。
- 【大分県商工会連合会事件(福岡高判 平成23年9月27日)】
この事例では、退職金が約135万円減額される変更が行われましたが、裁判所はこれを無効と判断しました。
裁判所は、経営状況から変更の必要性自体は認めつつも、約135万円という減額は看過できない不利益であり、変更の必要性は認められるが減額の幅が相当であるかには疑問があり、代償措置が減額に対応するものとなっておらず、労働者側の反対を押し切って変更されたものであること等を理由に、退職金の減額に合理性ありと認めることはできず、変更を無効と判断しました。
「会社のためなら、従業員も多少の痛みは分かってくれるはずだ。」 そう信じたいお気持ちは痛いほど分かりますが、法的な判断においては、一方的な不利益の押し付けは通用しないのが現実です。
2. 裁判所が見る「4つの判断基準」と「周知」
では、従業員の同意が得られなければ絶対に無理かというと、例外もあります。
労働契約法第10条では、変更内容が「合理的」であれば認められるとしています。
(労働契約法第10条) 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
ここで重要なのは、単に内容が合理的であるだけでなく、変更後の就業規則を労働者に周知させることも必須条件だという点です。
そして、「合理性」を判断するために、裁判所は主に以下の4つの要素をチェックします。
① 労働者が受ける不利益の程度
② 労働条件の変更の必要性
③ 変更後の内容の相当性(代償措置など)
④ 労働組合等との交渉の状況(プロセス)
特に重要なのが、①と②のバランスです。これを「相関関係」と呼びます。
① 労働者が受ける不利益の程度(必要性との相関関係)
ここが重要なポイントです。 「〇〇%までならOK」という法律上の安全圏はありません。
しかし、裁判所は「不利益の程度」と「変更の必要性」を天秤にかけて判断します(下記の第四銀行事件参考)。
- 第四銀行事件(最判 平成9年2月28日)
この判決では、「不利益が大きければ大きいほど、それを正当化するための必要性も高くなければならない」という基準(相関関係)があると示されました。
もし不利益が小さい(あるいは定年延長などの見返りで緩和されている)ならば、それを正当化する必要性は相対的に低くて済みます。
逆に、何割も減るような大きな不利益変更であれば、倒産回避レベルの「高度な必要性」がなければ認められません。
② 労働条件の変更の必要性
前述の通り、不利益が大きければ大きいほど、会社経営が危機的状況にあることの証明が求められます。
③ 変更後の内容の相当性(代償措置など)
ただ減らすだけなのか、代わりの措置はあるか?
裁判所は、不利益を軽減・補償するための代償措置の有無とその内容を重視します。
代償措置の具体例:
【金銭的な代償措置】
- 退職金の減額分を基本給や諸手当に上乗せする
(例:退職金を20%削減する代わりに、基本給を月額1万円増額する) - 確定拠出年金制度(DC)の導入や企業型年金の拠出額増額
(退職一時金から年金制度への移行により、従業員の老後資金形成を支援) - 特別一時金の支給
(制度変更時に、これまでの貢献に対する感謝の意を示す)
【経過措置・激変緩和措置】
- 年齢・勤続年数による段階的適用
(例:50歳以上の従業員には旧制度を適用、40代は減額幅を半分に、30代以下は新制度を全面適用) - 経過措置期間の設定
(例:向こう5年間は減額幅を段階的に拡大し、6年目から新制度を全面適用) - 既得権の保護
(例:変更時点までに積み上がった退職金相当額は旧基準で保証する)
【その他の配慮】
- 再雇用制度の充実
(定年後の再雇用条件を改善し、長く働ける環境を整備) - 福利厚生の拡充
(退職金は減らすが、住宅手当や資格取得支援制度を新設・拡充) - 昇給・昇格制度の改善
(若手・中堅層の昇給ピッチを早め、将来的な賃金総額で補償)
代償措置は、「単に何かを与えればよい」というものではありません。
減額によって生じる不利益と、代償措置による利益のバランスが取れているかが問われます。
また、代償措置の内容を従業員に対して明確に説明し、理解を得ることも重要です。
④ プロセス(労働組合等との交渉)
労使で誠実に話し合ったか?
会社側が情報を開示し、労働組合や従業員と粘り強く協議を重ねた事実が必要です。
【労働組合がある企業の場合】
労働組合との団体交渉を複数回実施し、会社の経営状況や変更の必要性について、財務データなどの客観的資料を示しながら誠実に説明し、協議を尽くすことが求められます。
【労働組合がない企業の場合】
労働組合がないからといって、一方的に変更できるわけではありません。
以下のような対応が必要です
- 従業員の過半数代表者との協議・意見聴取
(労働基準法で定める「過半数代表者」を適正な手続きで選出し、その代表者と誠実に協議する) - 説明会を複数回開催
(経営状況、変更の必要性、変更内容、影響の程度などを丁寧に説明し、質疑応答の時間を十分に設ける) - 個別面談の実施
(特に影響の大きい従業員については、個別に面談し、不安や疑問に真摯に対応する) - 質問・意見を受け付ける窓口の設置
(書面やメールでの質問も受け付け、回答を全従業員に共有する)
「形式的に説明会を1回開催した」だけでは不十分です。
従業員が納得するまで、繰り返し対話の機会を設けることが、プロセスの誠実性を示す証拠となります。
「周知」は合理性と並ぶ必須要件
労働契約法第10条では、変更内容が合理的であることに加えて、変更後の就業規則を労働者に周知させることが明確に要求されています。
つまり、どれほど合理性があっても、周知が不十分であれば変更は無効となる可能性があります。
周知の具体的な方法としては、以下のようなものがあります
- 就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示、または備え付ける
- 書面で交付する
- 社内イントラネットや共有フォルダに掲載し、いつでも閲覧できるようにする
- 説明会を開催し、変更内容を直接説明する
特に退職金のような重要な労働条件の変更については、単に掲示するだけでなく、説明会を開催し、変更の内容・理由・影響について丁寧に説明することが推奨されます。
3. 成功と失敗の分かれ道(判例比較)
実際の判例を見ると、その境界線がより鮮明になります。
- 【認められなかった例:御國ハイヤー事件(最判 昭和58年7月15日)】
会社が退職金規定を廃止し、その期間を勤続年数に入れないとしたケースです。
裁判所は「代償措置が何もなく、一方的に不利益を課すもの」として、変更を無効としました。
- 【認められた例:日刊工業新聞社事件(東京高判 平成20年2月13日)】
退職金を50%も削減するという大幅な変更でしたが、裁判所はこれを有効と認めました。
この会社は当時、倒産か再建かの二者択一を迫られるほどの危機的状況にありました。
さらに、労働組合と誠実に協議し、できる限りの経営努力を行っていたことが評価されました。
【番外編:ルールの明確化なら認められやすい?】
一方で、金額の減額ではなく、「懲戒解雇されたときは退職金を払わない・減額する」という規定を新設する場合はどうでしょうか。
これは、まじめに働く通常の従業員には不利益がないため、比較的合理性が認められやすい傾向にあります。
ただし、「退職後に競業他社へ転職したら減額」という規定は、職業選択の自由との兼ね合いで慎重な配慮が必要です。
4. トラブルを避けるための実務ステップ
もしも、退職金制度の変更を決断せざるを得ないなら、以下のようなステップを進めることが必要です。
- プロジェクトチームの結成
経営陣だけでなく、弁護士や社会保険労務士といった専門家を交えたチームを作ります。 - 経営努力の徹底
従業員に痛みを求める前に、役員報酬の削減や経費の見直しなど、経営側ができることをすべて実行します。これが説得力の土台になります。 - 誠実な説明と「真の同意」の取得
ここが最大のポイントです。
【山梨県民信用組合事件(最判 平成28年2月19日)】
この事件では、合併のために退職金規定の変更が必要だと説明され、職員から同意書も提出されていました。
しかし最高裁は、この同意を無効と判断しました。
なぜなら、不利益の具体的な中身(実際にいくら減るのか等)について十分な情報提供や説明がなく、職員が自由な意思で判断できる状況ではなかったとされたからです。
「とりあえずハンコをもらえばいい」という形式的な同意では、法的な効力を持たないことがあります。
「合併のために必要だ」という会社側の事情だけでなく、「あなたにはこれだけの不利益がある」というマイナス面も包み隠さず説明し、その上で納得してもらうプロセスが不可欠です。 - 未来のビジョンの提示
「減らします」だけでなく、「制度を変えることで会社を存続させ、将来的にはこうやって還元したい」という前向きなビジョンをセットで語ることが大切です。
【まとめ】
今回の内容を整理すると以下のようになります。
- 退職金の減額・廃止は「労働条件の不利益変更」にあたり、原則として従業員の個別の同意が必要です。
- その同意は、形式的な署名だけでなく、十分な説明を受けた上での「自由な意思に基づく真の同意」でなければなりません(山梨県民信用組合事件)。
- 合意が得られない場合、変更を強行するには「高度な必要性」 「合理性」に加え、変更後の規則の「周知」が必要です(労働契約法第10条)。
- 不利益の程度と必要性は「相関関係」にあります。減額幅が大きいほど、倒産回避などの極めて高度な必要性が求められます(第四銀行事件)。
「この会社のためなら仕方ない、一緒に乗り越えよう」。
従業員の方々にそう思っていただけるよう、誠実な対話とプロセスを尽くすことが、結果として会社を守る一番の近道となります。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。

- 第2回:就業規則の届出方法 -変更・規程の新設・全条失効の方法も解説します。
- 交通事故で退職…その後の生活費、どうすれば?所得補償制度について解説します。
- 「雇用保険に関する業務取扱要領」を自動ダウンロード化できた話(DLファイル有り)
- 第1回:就業規則の基本中の基本 ― そもそも就業規則とは?
- 【就業規則】 第0回:就業規則をもっと身近に-就業規則について、今日から少しずつお話しします-

この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン
”ここまでやるかと言わせたい!”
【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、
「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。