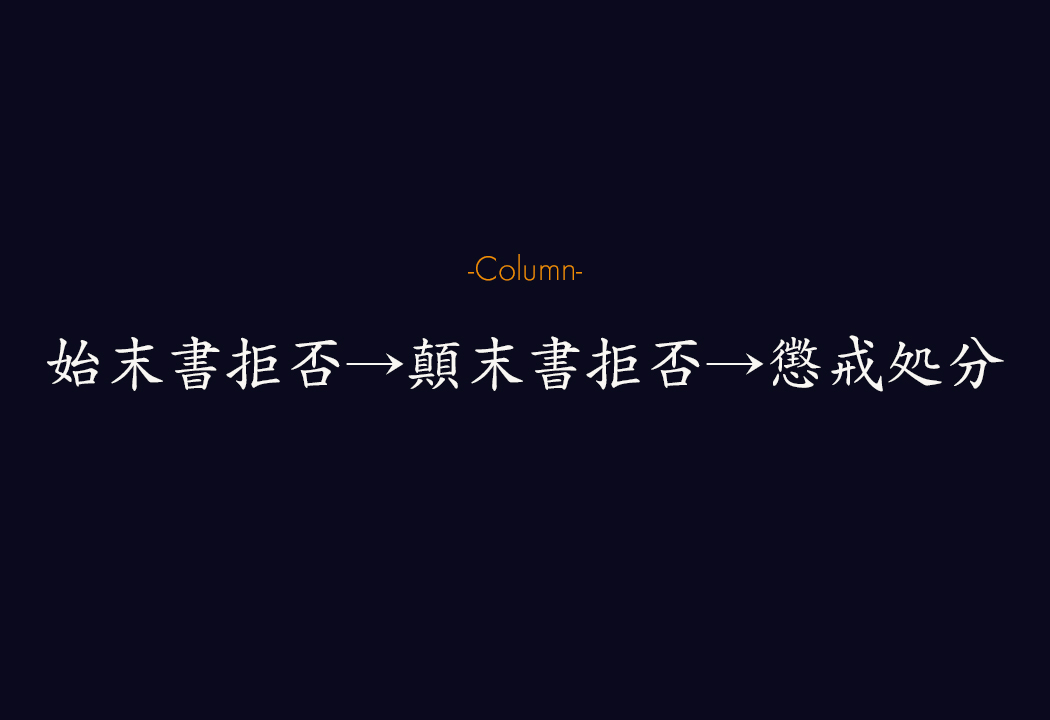【はじめに】
企業の労務管理において、「従業員が問題行動を起こしたものの、始末書の提出を拒否している」という状況、まれに質問を受けるのですが、企業にとって頭の痛い問題ではないでしょうか。
そこで、事実関係の報告を目的として「顛末書」の提出を業務命令として発したものの、それすらも拒否されてしまった…。
このようなケースで、「顛末書の不提出」を理由に、新たな懲戒処分を科すことは可能なのでしょうか。
この記事では、混同されがちな「始末書」と「顛末書」の違いを整理し、それぞれの提出拒否に対する懲戒処分の妥当性について、分かりやすく解説します。
【まずは結論】
結論から申し上げると、業務命令として発した「顛末書」の提出を正当な理由なく拒否する行為は、当初の非違行為とは別の、新たな懲戒事由(業務命令違反)に該当すると考えられます。
ただし、懲戒処分を有効に行うためには、「二重処罰の禁止」や「処分の相当性」といった法原則を遵守する必要があり、慎重な手続きが求められます。その理由をこれから詳しく見ていきましょう。
【解説】
1. なぜ「始末書」の提出は強制できないのか?
まず、大前提として「始末書」の提出を強制し、提出しないことを理由にさらに懲戒処分を科すことは、難しいということです。
「始末書」とは、単なる事実の報告書ではありません。従業員が起こした問題行動について、事実を認めさせ、反省と謝罪の意を表明させ、将来同じ過ちを繰り返さないことを誓約させる目的を持つ文書です。つまり、その内容には「深く反省しております」といった、個人の内面や心情の表明が含まれます。
この「反省や謝罪を強制すること」が、法的な壁に突き当たります。日本国憲法第19条は「思想及び良心の自由」を保障しており、心の中で何を思い、どう感じるかは国家権力であろうと強制できない、という基本的な権利です。
過去の裁判例(例:福知山信用金庫事件 大阪高判 昭和53.10.27)でも、内心の意思表示である反省や謝罪を強制することは、この憲法上の権利を侵害するおそれがあるとして、始末書の提出拒否を理由とした懲戒解雇を無効と判断しています。
つまり、始末書の提出命令は、懲戒処分(けん責など)の一環として行うことはできても、従業員が「反省していない」と提出を拒否した場合、それを無理強いすることはできないのです。
2. 「顛末書」が業務命令として有効な理由
一方で、「顛末書」は法的に全く異なる性質を持ちます。顛末書の目的は、あくまで発生した問題の一部始終(日時、場所、原因、経過など)を客観的な事実に基づいて報告させることにあります。
ここに従業員の反省や謝罪といった主観的な心情を記載する必要はありません。
このため、顛末書の提出命令は、懲戒権ではなく、労働契約に基づく使用者の広範な指揮命令権、すなわち「業務命令権」に基づいて行われます。従業員には、労働契約上の義務として、業務上必要な報告を行う義務があります。
客観的な事実報告を求める顛末書の提出は、この報告義務の一環と位置づけられるため、思想・良心の自由とは抵触せず、業務上の必要性が認められる限り、有効な業務命令となるのです。
したがって、従業員が正当な理由なくこの業務命令を拒否する行為は、単に「反省していない」という心情の問題ではなく、明確な「業務命令違反」という契約上の義務違反に該当すると考えられます。
この違いを明確にするために、両者を比較してみましょう。
| 項目 | 始末書 | 顛末書 |
|---|---|---|
| 目的 | 反省・謝罪の意思表明、再発防止の誓約 | 客観的な事実関係の報告、原因究明 |
| 内容 | 主観的要素(反省文・謝罪文)を含む | 客観的事実の経緯報告に限定 |
| 命令の根拠 | 懲戒権 | 業務命令権 |
| 提出の強制力 | 限定的(思想・良心の自由) | 原則として強制可能(正当な業務命令として) |
| 提出拒否への対応 | 新たな懲戒処分は無効となる可能性が高い | 業務命令違反として新たな懲戒処分の対象となり得る |
3. 懲戒処分を行う際の3つの「鉄則」
顛末書の提出拒否が懲戒処分の対象となり得るとしても、実際に処分を行う際には、以下の3つの重要なポイントを必ず守る必要があります。これを怠ると、処分が無効と判断されるリスクが高まります。
- ポイント1:「二重処罰」にならないよう明確に区別する
「同じ失敗で二度罰しない」という「二重処罰禁止の原則」は、懲戒処分においても重要な原則です。今回のケースでこの原則に抵触しないためには、処分の対象となる行為を明確に分けることが不可欠です。- 最初の処分(けん責):当初の問題行動そのものに対する処分
- 今回の新たな処分:「顛末書の提出を命じた業務命令への違反」という、全く別の行為に対する処分
懲戒処分通知書には、処分の理由を「〇年〇月〇日付の顛末書提出命令に対する業務命令違反」と具体的に記載し、当初の非違行為とは別の事案であることを明確にしましょう。
- ポイント2:就業規則に「業務命令違反」の定めがあるか確認する
懲戒処分は、必ず就業規則に定められた事由と種類に基づいて行わなければなりません(労働基準法第89条)。
貴社の就業規則に、懲戒事由として「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」といった規定があるか、確認してください。この根拠規定がなければ、懲戒処分は無効となる可能性があります。 - ポイント3:処分の重さが適切か
「顛末書を提出しない」という行為に対して、いきなり解雇や出勤停止のような重い処分を科すことは、行為と処分のバランスを欠き、「懲戒権の濫用」として無効と判断される可能性が高いでしょう(労働契約法第15条)。
この場合、最も軽い懲戒処分である「けん責」や、あるいは労働基準法第91条の範囲内での「減給」などが、社会通念上相当な処分の範囲と考えられます。従業員の過去の勤務態度なども考慮し、慎重な判断が必要です。
【まとめ】
今回の内容を整理すると、以下のようになります。
- 「始末書」は反省や謝罪を求めるものであり、提出の強制は憲法が保障する「思想・良心の自由」を侵害するおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
- 一方、「顛末書」は客観的な事実報告を求めるものであり、業務上の必要性があれば「業務命令」として発することができます。
- 正当な理由なく顛末書の提出命令を拒否する行為は、「業務命令違反」として新たな懲戒処分の対象となり得ます。
- 懲戒処分を行う際は、「二重処罰にならないこと」「就業規則に根拠があること」「処分の重さが相当であること」「弁明の機会を与えるなど手続きが適正であること」が必要です。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。