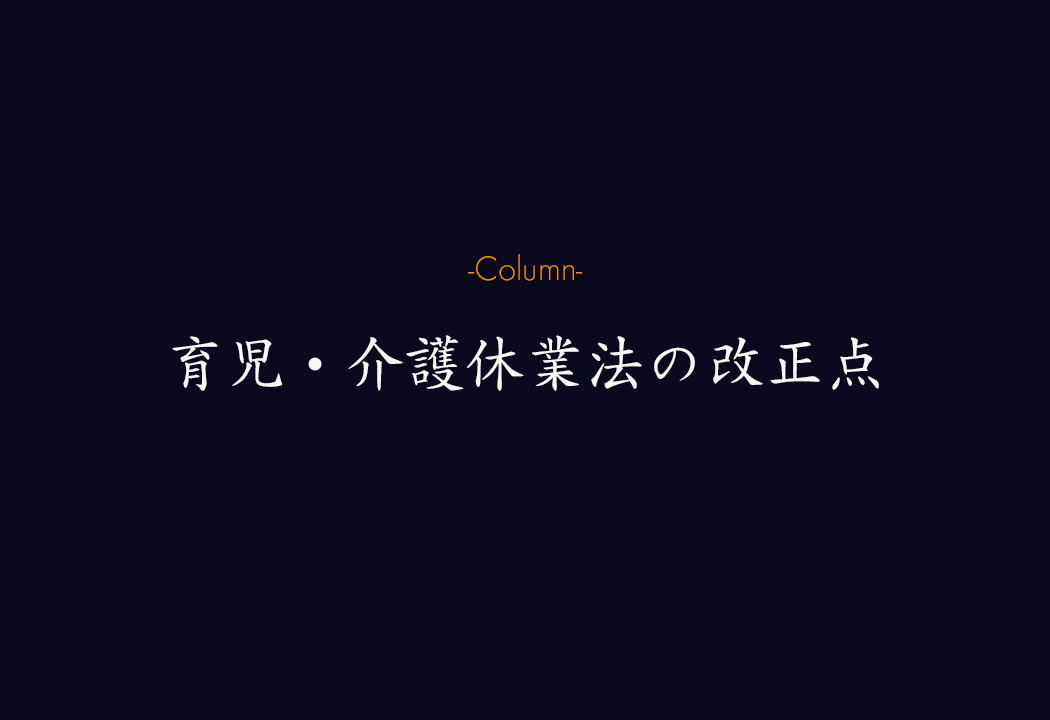【はじめに】
「2025年から育児・介護休業法が大きく変わるけれど、具体的に何がどう変わるのか、自分に関係あるのかよく分からない…」と悩んでいませんか?
今回の法改正は、育児や介護をしながら働くすべての方、そして従業員を雇用するすべての企業にとって非常に重要な内容ですが、とても複雑な改正内容となっております。この記事では、2025年4月と10月に施行される育児・介護休業法の主な改正点を、分かりやすく解説します。
【ポイント】
今回の法改正の最も重要なポイントは、「育児や介護をしながらでも、より柔軟に働き続けられる環境を整えること」にあります。
子の看護休暇の対象拡大や、介護離職を防ぐための取り組みが強化されるなど、仕事と家庭の両立を支援する制度がこれまで以上に手厚くなります。
【解説】
1. 2025年4月1日から施行される主な改正点
2025年4月より、仕事と家庭の両立を支えるため、育児・介護に関する制度が幅広く見直されます。特に影響の大きい項目を解説します。
- (1) 子の看護休暇の対象拡大
これまでは「小学校就学前」の子どもが対象だった子の看護休暇ですが、改正後は「小学校第3学年修了前」までに引き上げられます。また、これまでは労使協定によって入社6か月未満の従業員を対象外とすることができましたが、その要件が撤廃されます。これにより、入社後すぐであっても制度を利用できるようになります。さらに、子の入学式といった行事への参加も取得事由として追加されるなど、より利用しやすい制度へと変わります。
名称も子の看護等休暇となります。
- (2) 所定外労働の制限となる子の範囲の拡大
子育て中の従業員が請求できる 所定外労働の免除について、対象となる子の年齢がこれまでの「3歳まで」から「小学校就学前」までに延長されます。これにより、子どもが小学校に上がるまでの期間、より柔軟な働き方が可能となるでしょう。
【所定外労働とは…あらかじめ契約した労働時間を超えて働くことです。】
- (3) 育児休業取得状況の公表義務が拡大
従業員の育児休業取得状況について、企業に公表が義務付けられています。この対象が、これまでの「常時雇用する労働者が1,000人超」の企業から、「300人超」の企業へと拡大されます。
- (4) 介護に関する制度の拡充
介護離職の問題は、多くの企業にとって大きな課題です。今回の改正では、介護離職を防ぐための企業の取り組みが強化されます。まず、介護休暇については、子の看護等休暇と同様に、入社6か月未満の従業員を対象外とする労使協定の定めが無効となります。これにより、入社後すぐに家族の介護が必要になった場合でも、休暇を取得できるようになります。
加えて、「介護に関する研修の実施」や「相談窓口の設置」といった雇用環境の整備が義務となります。
また、従業員本人やその家族が介護に直面した旨の申し出があった場合、企業は個別に利用できる制度を周知し、利用意向を確認することが義務付けられます。さらに、従業員が40歳に達した際など、早い段階で介護に関する情報提供を行うことも求められます。
- (5) 新たな給付金の創設
育児休業中の経済的な不安を和らげるため、新たな給付金が創設されます。夫婦ともに育児休業を取得した場合に給付が上乗せされる「出生後休業支援給付」や、2歳未満の子を養育しながら短時間勤務制度を利用する従業員を支援する「育児時短就業給付」が新たに始まります。
- (6) 育児・介護におけるテレワーク導入の努力義務化
今回の改正では、育児や介護を行う従業員がより柔軟に働けるよう、テレワークの導入が推奨されます。具体的には、「3歳までの子を育てる従業員」および「対象家族を介護する従業員」が利用できる措置として、企業がテレワーク等を導入することが努力義務となります。
2. 2025年10月1日から施行される主な改正点
2025年10月からは、特に3歳以上の子どもを育てる従業員の働き方に大きな変化が生まれます。
- (1) 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
「3歳から小学校就学前の子」を養育する従業員が利用できる働き方の選択肢を増やすことが、企業に義務付けられます。具体的には、以下の措置の中から2つ以上を講じ、従業員がその中から1つを選択して利用できるようにしなければなりません。- フレックスタイム制又は時差出勤の制度
- 在宅勤務等(テレワーク)
- 育児短時間勤務
- 養育両立支援休暇の付与(新たな休暇制度)
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
- (2) 個別の意向聴取と配慮の義務化
今回の改正で、仕事と育児の両立支援をより実質的なものにするため、企業が従業員の意向を聴き取り、配慮することが新たに義務付けられました。これは対象者によって対応が異なります。- 妊娠・出産を申し出た従業員に対して
従業員から妊娠・出産について申し出があった場合、企業は利用できる制度を知らせる「個別周知」と「意向確認」に加えて、さらに一歩踏み込んだ「個別の意向聴取」およびその意向への「配慮」を行うことが新たに義務となります。 - 3歳未満の子を養育する従業員に対して
子が3歳になるまでの従業員に対しては、企業が講じている柔軟な働き方の措置(テレワーク、時短勤務など)について、「個別周知」「意向確認」「意向聴取」「配慮」の4つをすべて行うことが義務付けられます。これにより、従業員一人ひとりが自身の状況に合わせて制度を選択しやすくなることが期待されます。
- 妊娠・出産を申し出た従業員に対して
【まとめ】
今回は令和7年の育児介護休業法の改正について、解説をしました。毎年のように改正が行われる育児介護休業法は、実務担当者だけでなく、社労士にとっても非常に難解な仕組みとなってきていることを痛感しております。
もしも制度でお困りの際や、育児・介護休業規程の改定でお困りの際は、お力になりますので何なりとお申し付けくださいませ。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。