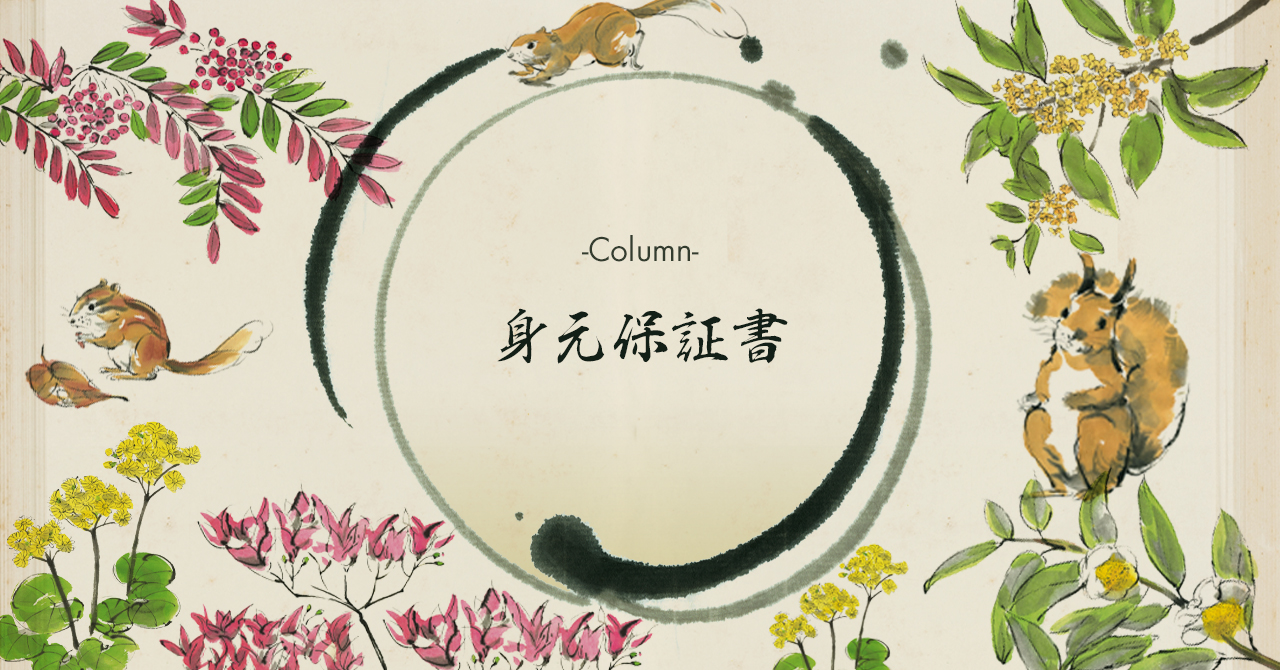【極度額は定められていますか?】身元保証契約の注意点
【はじめに】
新しく従業員を採用する際、万が一の事態に備えて「身元保証書」を提出してもらうケースは多いと思います。
しかし、2020年4月1日の民法改正により、身元保証契約のルールが大きく変わったことをご存知でしょうか。
もし、古いひな形をそのまま使い続けていると、その身元保証契約は「無効」になっている可能性が高いです。
私の経験上、身元保証書を改正があったと知らずに、昔からのひな形を使い続けているケースは意外と多いです。
今回は、身元保証に関する注意点を分かりやすく解説します。
【まずは結論】
2020年3月までは、身元保証人は特に取り決めがなければ、無限に損害を保証するということになっていましたが、2020年4月1日以降に締結した身元保証契約については、「保証してもらう金額の上限(=極度額 きょくどがく)」を契約書に具体的に定めておかなければ、その身元保証契約は無効となります。
【解説】
1. 身元保証契約の目的(意義)
そもそも、なぜ多くの企業が身元保証書を必要とするのでしょうか。
主な目的は以下の3点に整理されることが多いです。
(1) 損害発生時の金銭回収
従業員が業務に関連して会社に損害を与えた場合、例えば着服や横領、あるいは近年問題となるSNSへの不適切な投稿による信用の毀損などが考えられます。こうした損害が多額になると、従業員本人だけの資力では賠償(返済)が難しいケースも多くあります。
その際、身元保証人がいれば、会社は金銭回収の確実性を高めることができます。
(2) 従業員の規律意識の向上
「もし自分が問題を起こせば、保証人になってくれた家族などに迷惑がかかる」という意識が、従業員自身の誠実な勤務態度や不正行為への心理的な抑止力として機能することが期待されます。
(3) 緊急時の連絡先
これは法律上の目的とは少し異なりますが、実務上は重要な役割です。
従業員本人が行方不明になったり、心身の不調が疑われたりする際に、ご家族でもある保証人へ連絡し、状況を相談するための窓口としての機能も担っています。
2. なぜ「極度額」が必須になったのか(2020年4月 民法改正)
身元保証契約は、従業員の行為によって会社が損害を被った場合に、身元保証人に賠償してもらうことを目的としています。
しかし、2020年3月までは、賠償額の上限(いくらまで保証するのか)を具体的に定めない契約も多く見られました。
これでは、保証人の方が予期せぬ巨額の賠償責任を負うリスクがあり、安心して保証人を引き受けることが難しくなっていました。
そこで、保証人を保護する目的で民法が改正され、2020年4月以降に締結する身元保証契約については、上限金額(極度額)を契約書に明記することが義務付けられました(民法第465条の2第2項)。
極度額の定めがない身元保証契約は、契約自体が「無効」となりますので、注意が必要です。
3. 契約書OK例・NG例
- (NG例:無効)
「本人の行為により会社が被った一切の損害を賠償する」
→ このように、具体的な金額の上限(極度額)が書かれていない契約書は無効となります。 - (OK例:有効)
「本契約に基づく保証の極度額は、金〇〇万円とする」
→ このように、具体的な金額を明記する必要があります。
4. 「身元保証ニ関スル法律」のルール(契約期間と自動更新)
民法改正とは別に、以前から存在する「身元保証ニ関スル法律」という法律のルールも、もちろん引き続き適用されます。
特に注意が必要なのは「契約期間」です。
- 契約期間
- 期間の定めがない場合:法律上「3年」となります(身元保証ニ関スル法律第1条)。
- 期間を定めた場合:最長でも「5年」となります。5年を超える期間(例:10年)を定めても、法律上「5年」に短縮されます(身元保証ニ関スル法律第2条)。
- 契約の更新(再取得のタイミング)
- 契約の更新は可能ですが、「自動更新」の定め(例:「期間満了後は1年間自動で更新する」といった条項)は認められません。
- 期間が満了するたびに(例えば5年ごとや3年ごとに)、会社から従業員に再提出を求めると、従業員に対して「いつまでも信用されていない」という印象を与えかねず、会社の管理も煩雑となり、実務上は難しいケースもあります。
- そこで実務上は、従業員が「昇進」や「異動(配置転換)」、「出向」などで、職務内容や責任の範囲が大きく変わるタイミングに合わせて、改めて身元保証書を再取得する(取り直す)と規定している企業が多いです。
これは、本人に責任の重さを改めて自覚してもらうという意味でも合理的なタイミングと考えられるでしょう。
5. 会社(使用者)の「通知義務」
身元保証契約を締結すると、会社側には保証人に対して「特定の事情が認められた場合は通知しなければならない義務」が発生します(身元保証ニ関スル法律第3条)。
もし会社がこの通知を怠ってしまうと、後に損害が発生した際、保証人に対して賠償を請求できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
会社が保証人に通知すべき「事情が認められた場合」とは、具体的に以下の2点です。
- 従業員に問題行動があったとき
従業員に業務上の不適任または不誠実な行いがあり、その結果として「将来、身元保証人が賠償責任を負うことになるかもしれない」と思われる場合。
例えば、私的な飲食代を交際費として請求したことが発覚した場合、初回は軽い懲戒処分(訓戒等)で済ませたとしても、保証人からすれば「将来、より大きな問題を起こすかもしれない」と判断する材料になります。 - 従業員の任務や勤務地が変更されたとき
従業員の仕事内容や勤務地が変更になり、それによって保証人の責任が重くなったり、あるいは勤務地が変更され、保証人による監督(例えば、同居している親が保証人の場合など)が難しくなったりすると思われる場合。
これらの事実が発生した際は、会社は遅滞なく身元保証人に通知することが求められます。
6. 実務上のアドバイス
身元保証は、万が一の際の金銭回収の確実性を上げる目的があります。
しかし、極度額を定めた有効な契約書があっても、裁判所が常にその上限額までの全額の支払いを命じるとは限りません。
例えば、仮に「極度額100万円」という有効な契約があり、従業員が80万円の損害を出したとします。
この場合、極度額の範囲内だからといって、裁判所が必ずしも保証人に80万円全額の支払いを命じるとは限らないのです。
実際の裁判では、「会社側の監督体制に不備はなかったか?」「損害の発生を予防する努力を怠っていなかったか?」といった、会社側の監督責任も問われることになります。その結果、保証人の責任は、発生した損害額の一部(例えば損害額の2割~5割程度など)に減額されるケースが多いのが実情です。
身元保証はあくまでも万が一の備えの一つであることを理解し、日頃の労務管理体制をしっかり整えていくことが、企業のリスク管理の基本となると考えられます。
【まとめ】
今回の内容を整理すると以下のようになります。
- 2020年4月1日以降に締結する身元保証書には、必ず「極度額(賠償の上限金額)」を具体的に記載してください。記載がない契約は無効です。
- 契約期間は、定めがなければ3年、定めても最長5年です。
- 契約の「自動更新」は認められません。期間満了時の再取得は、昇進・異動などのタイミングで行うのが実務的です。
- 従業員に問題行動があった場合や責任が重くなる配置転換等をした場合は、会社から身元保証人へその事実を通知する義務があります。
- まずは、会社で使用している「身元保証書」のひな形に「極度額」の記載欄があるか、確認することをお勧めします。
【参照元】
- 法務省:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります
- e-Gov法令検索:身元保証ニ関スル法律
- e-Gov法令検索:民法
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。

この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン
”ここまでやるかと言わせたい!”
【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。