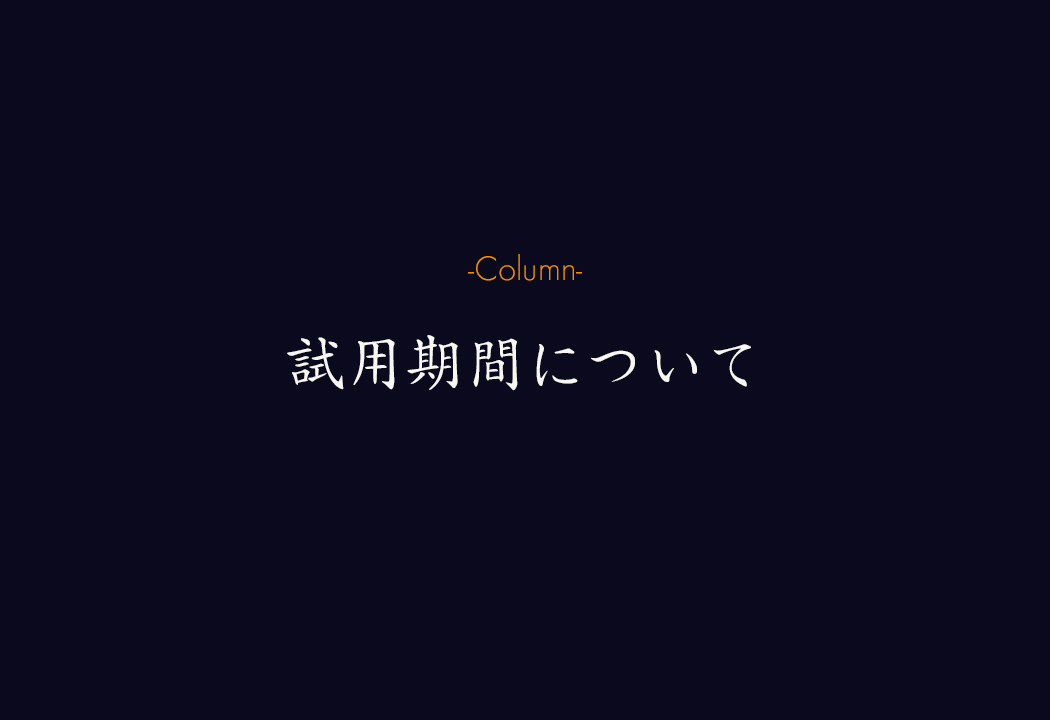【はじめに】
「試用期間中の社員が、期待した能力ではなかった」「職場の雰囲気に合わないようだ」
そう感じたとき、「本採用をしなければ問題ない」と考えていませんか?
試用期間は、多くの企業で設けられている制度です。
しかし、その法的な意味や、期間終了時の対応(本採用拒否)について、誤解が生じやすい点でもあります。
この記事では、試用期間の基本的なルールと、特にトラブルになりやすい「試用期間中の解雇」および「試用期間経過後の本採用拒否」について、分かりやすく解説します。
【まずは結論】
試用期間を設けて採用した場合でも、採用した時点で「労働契約」は成立しています。
これは「解約権留保付の労働契約」と呼ばれるものです。
そのため、試用期間が終了した際に本採用を拒否することは、法律上「解雇」にあたります。
また、試用期間の「途中」で契約を打ち切ることも、もちろん「解雇」です。
「解雇」である以上、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められなければ、その権利を濫用したものとして無効となる可能性があります(労働契約法第16条)。
【解説】
1. 試用期間とは?
試用期間は、法律で定められた制度ではありませんが、多くの企業が、就業規則などで「従業員としての適格性」を判断する期間として設けています。
法的には「解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき)の労働契約」と解されています。
この言葉は非常に難しく聞こえるかもしれません。
これを分かりやすく言うと、「採用は決定し、労働契約は始まっています。ただし、『もし試用期間中に、会社の従業員として不適格だと判断した場合は、会社側から契約を終了(解約)できる権利』を、会社側が持っている(留保している)状態の契約」ということです。
ポイントは、試用期間であっても、採用時点で労働契約は成立している、という点です。
2. 試用期間の長さ・延長について
試用期間の長さ(上限)は、法律で決まっていません。
しかし、あまりに長い期間は公序良俗に反し、無効と判断される可能性があります。
一般的には3か月から6か月程度とするケースが多いです。
また、試用期間の延長は、会社の都合だけで自由に行えるものではありません。
あらかじめ就業規則や労働契約書に「延長の可能性があること」と「その理由」を明記しておくことが必要です。
その上で、延長するための合理的な理由(例:病気で長期欠勤し、適格性を判断できなかった等)が必要と考えられるでしょう。
3. 「本採用拒否」が「解雇」になる理由
上記1.の通り、試用期間は「解約権留保付の労働契約」です。
期間契約(有期雇用契約)とは異なり、期間満了時に「契約を更新しない」という選択とは性質が異なります。
試用期間の終了時に本採用をしない、ということは、会社側が「契約を解約する権利」を行使することになります。
そのため、法的な性質は「解雇」そのものとなります。
4. 本採用拒否(解雇)が認められる「正当な理由」とは
「解雇」である以上、客観的に合理的な理由と社会的な相当性が必要です。
ただし、この点に関する最高裁判所の判例(三菱樹脂事件・最判昭48.12.12等)に基づき、試用期間の趣旨(適格性判断)から、通常の解雇よりは広い範囲で解雇の自由(裁量)が認められる傾向にある、と解されています。
とはいえ、無制限の自由ではなく、あくまで「採用時に知ることができなかった事実(勤務態度の不良など)が判明し、引き続き雇用することは適当でない」と客観的・合理的に判断できる必要があります。
認められやすい理由の例としては、以下のようなものが考えられます。
- 経歴詐称:応募時に提出された履歴書などで、重要な経歴を偽っていたことが判明した場合。
- 勤怠不良:無断欠勤や遅刻を繰り返し、会社が指導しても改善されない場合。
- 協調性の欠如:他の従業員と著しくトラブルを起こすなど、業務に支障をきたし、指導しても改善が見られない場合。
- 能力不足:会社側が十分な指導や教育を行っても改善が見られず、期待された業務を遂行する最低ラインに達しないと客観的に判断される場合。
重要なのは、会社側が十分な指導・教育を行ったか、改善の機会を与えたか、という点です。何も指導していないのに「能力不足だ」として本採用を拒否することは、問題となる可能性が高いでしょう。
5. 「試用期間中の解雇」と「本採用拒否」の法的な難易度
この二つは、同じ「解雇」でも法的なハードルが異なります。
- 試用期間満了による「本採用拒否」
上記4.の通り、これは「留保解約権の行使」にあたります。
試用期間の趣旨に基づき、「見極めた結果、適格性がない」と判断する行為であるため、通常の解雇よりは広い裁量が認められます(ただし、ハードルは高いです)。 - 試用期間の「途中」での解雇
これは、試用期間の趣旨(見極める期間)を会社が自ら放棄する行為と見なされます。
この点について、参考になる裁判例があります(ニュース証券事件・東京地裁 平21.1.30)。
この事件では、試用期間の途中に行われた解雇が争われました。
裁判所は、「そもそも試用期間は適格性を見極めるための期間なのだから、原則として会社は期間満了まで見極めるべき」であり、期間の途中で解雇することはより一層高度の合理性と相当性が求められるとし、「解雇権の濫用」にあたり無効である、と判断しました。
このように、試用期間の「途中」での解雇のハードルは「極めて高い」と考えられます。
よほどの重大な非違行為がない限り、認められにくいでしょう。
6. 試用期間中の解雇予告
試用期間中であっても、解雇予告の手続きは原則として必要です。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
・試用期間の設定における注意点
例えば、3か月(90日)の試用期間を設定した場合、試用期間満了時に本採用を拒否するには、次のいずれかの方法をとる必要があります。
① 試用期間開始から60日目までに本採用拒否を決定・予告する
→ 30日後(=試用期間満了日)に解雇となる
→ 解雇予告手当の支払いは不要
② 試用期間満了日(90日目)に本採用拒否を通知する
→ 同時に解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う
→ 即日解雇が可能
このように、試用期間を設計する際は、判断のタイミングと解雇予告手当の支払いの有無を考慮する必要があります。
ただし、例外があります。
試用期間の開始から「14日以内」に解雇する場合は、この解雇予告制度は適用されません(労働基準法第21条)。
逆に言えば、採用から14日を超えていれば、試用期間中(例えば1か月経過時点)に解雇する場合でも、本採用拒否(試用期間満了時)の場合でも、解雇予告(または手当の支払い)が必要となります。
なお、14日以内であれば解雇予告は不要ですが、これは単に手続き上の例外であり、解雇そのものには客観的・合理的な理由と社会的相当性が必要です。
【まとめ】
今回の内容を整理すると以下のようになります。
- 試用期間は「解約権留保付の労働契約」であり、採用時点で労働契約は成立しています。
- 試用期間経過後の「本採用拒否」は、法的に「解雇」として扱われます。
- 試用期間の「途中」での解雇は、高度の合理性と相当性が求められ、ハードルは極めて高いといえます。
- 本採用拒否(解雇)を行うには、客観的に合理的な理由と社会的な相当性が必要です。会社側は十分な指導・教育を行ったかどうかが問われます。
- 採用から14日を超えていれば、試用期間中であっても解雇予告(または解雇予告手当の支払い)が必要です。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
【参照元】
・三菱樹脂事件(最判昭48.12.12)
・ニュース証券事件(東京地裁 平21.1.30)
↓【最近の投稿記事はこちら】↓
- 第1回:就業規則の基本中の基本 ― そもそも就業規則とは?
- 【就業規則】 第0回:就業規則をもっと身近に-就業規則について、今日から少しずつお話しします-
- パワハラの相談がきたらどう動く? 調査・判断・解決までをわかりやすく解説
- 【管理職向け】現場で迷うパワハラの定義と具体例―部下の主観だけで決まるわけではありません
- フレックスタイム制の実務と運用|残業計算からメリット・デメリットまでわかりやすく

この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン
”ここまでやるかと言わせたい!”
【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。