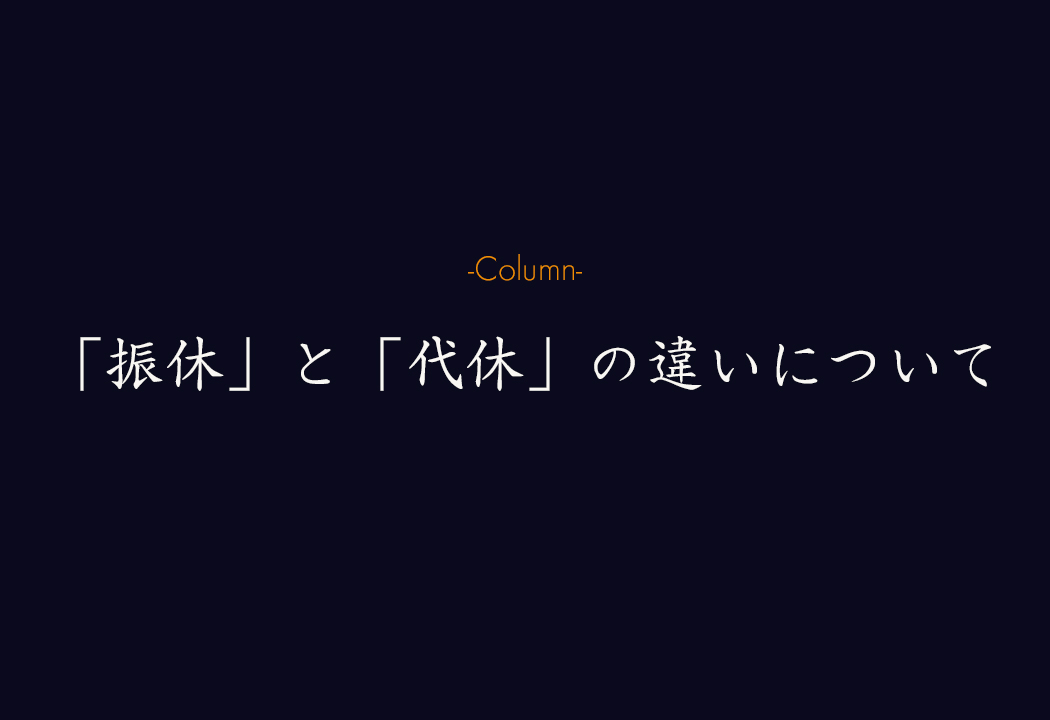「振替休日」と「代休」、同じようで全く違う!残業代未払いを防ぐための基礎知識
【はじめに】
「休日に出勤した代わりに、後日休みを取る」といった対応は、多くの職場で行われています。しかし、その休みが「振替休日」なのか、それとも「代休」なのか、正しく区別できているでしょうか。
この二つは似ているようで、意味合いや給与計算の方法が異なります。特に人事労務を担当される方や管理職の方がこの違いを理解していないと、意図せずして「残業代の未払い」という重大なコンプライアンス違反を犯してしまう可能性があります。
この記事では、「振替休日」と「代休」の明確な違いと、それぞれどのような場合に割増賃金の支払いが必要になるのかを、具体的な事例を交えて解説します。
【まずは結論】
「振替休日」と「代休」の最も重要な違いは、休日と労働日を「事前」に入れ替えるか、「事後」に休みを取得するかという点にあります。
- 振替休日: 事前に休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることです 。この場合、元々の休日は労働日となるため、「休日労働」にはならず、休日労働に対する割増賃金の支払いは原則として不要です 。
- 代休: 事後に、休日労働を行った代償として、他の労働日の勤務を免除することです 。休日労働を行った事実は変わらないため、「休日労働」に対する割増賃金の支払い義務が発生します 。
この違いを理解することが、適切な労務管理と給与計算の第一歩となります。
【解説】
1. 「振替休日」とは?
振替休日とは、あらかじめ就業規則などで「休日の振替を行うことがある」旨を定めた上で、業務の都合により、本来休日であった日を労働日とし、その代わりに別の労働日を休日に指定することを指します。この手続きは、必ず事前に行う必要があります 。
- ポイント: 事前に休日と労働日を入れ替えるため、元々の休日に労働しても「休日労働」扱いにはなりません。したがって、休日労働に対する割増賃金の支払いは不要となります 。
2. 「代休」とは?
代休とは、休日労働が行われた後に、その代償として、事後的に他の労働日を休みとすることです。振替休日と違い、事前の手続きはありません 。
- ポイント: 休日に労働した事実は変わりませんので、その日の労働は「休日労働」となります 。そのため、法定休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払う義務があります。その後、代休を取得した日の賃金を支払わないことは可能ですが、すでに発生した割増賃金の支払い義務がなくなるわけではありません。(1.35-1=0.35 0.35の割増賃金は必要)
3. 【重要】振替休日の注意点 – 割増賃金が発生するケース
振替休日は休日労働の割増賃金が発生しないため、会社側にとっては便利な制度に見えます。しかし、注意しないと「時間外労働」の割増賃金が発生するケースがあります。
振替休日を取得した日と、その代わりに労働した日が同じ週内であれば、週の労働時間は変わらないため、多くの場合、割増賃金の問題は生じません。
しかし、週をまたいで休日を振り替えた結果、労働した週の法定労働時間(原則週40時間)を超えてしまうことがあります 。その超えた時間については、時間外労働として2割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。
これが実務上、見落としがちな「盲点」と言えるでしょう。
- 事例:1日の所定労働時間8時間、週休2日制(土日休み)の会社の場合
- ケース1(週内で振替): 第1週の土曜日に出勤する代わりに、同じ週の木曜日を振替休日とした。
- → 第1週の労働時間は「月(8h)・火(8h)・水(8h)・木(休)・金(8h)・土(8h)」となり、合計40時間です。このため、割増賃金は発生しません。
- ケース2(週をまたいで振替): 第1週の土曜日に出勤し、翌週(第2週)の火曜日を振替休日とした。
- → 第1週の労働時間は「月(8h)・火(8h)・水(8h)・木(8h)・金(8h)・土(8h)」となり、合計48時間となります。週の法定労働時間40時間を超えた8時間分については、時間外労働として2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です 。
- ケース1(週内で振替): 第1週の土曜日に出勤する代わりに、同じ週の木曜日を振替休日とした。
4. 代休の割増賃金計算の具体例
代休を取得した場合、割増賃金の支払いはどうなるのでしょうか。以下の事例で確認してみましょう。
- 事例:1日の所定労働時間7.5時間、割増率2割5分の会社で、所定休日(土曜日)に7.5時間労働し、後日代休を取得した場合
- まず、休日出勤した7.5時間分の賃金を計算します。この日の労働により、週の総労働時間は37.5時間から45時間になりました。
- 週の法定労働時間40時間を超えた部分(5時間)は、時間外労働として割増賃金の対象となります。
- 割増の不要な部分(法定内残業):2.5時間 × 賃金単価 × 1.0
- 割増の必要な部分(法定外残業):5時間 × 賃金単価 × 1.25
- 一方で、後日代休を取得した日の賃金(7.5時間 × 賃金単価 × 1.0)を控除します。
- 結果として、会社は差額である「5時間 × 賃金単価 × 0.25」分の割増賃金を支払う必要があります。代休を取得したからといって、割増賃金の支払い義務が消えるわけではないのです。
5. 実務上のポイント
このような複雑さやトラブルを避けるために、以下のような対策が考えられます。
- 振替休日は「同一週内」を原則とする: 就業規則に「休日の振替は、原則として同一週内に行う」と規定することで、週をまたぐことによる時間外労働の発生を抑制できます。
- 週の起算日を見直す: 多くの会社では、就業規則に特に定めがなければ、週の起算日は日曜日となります 。これを例えば土曜日に変更することで、土曜日に出勤しても週の労働時間が40時間を超えにくくなる場合があります。ただし、この変更は就業規則の改定が必要になります。
【まとめ】
今回は、「振替休日」と「代休」の違いについて解説しました。最後に要点を整理します。
- 最も大きな違いは手続きのタイミングです。振替休日は「事前」に、代休は「事後」に行われます 。
- 振替休日は、元々の休日が労働日になるため「休日労働」とはならず、休日労働の割増賃金は発生しません 。
- ただし、振替休日が週をまたぐことで、出勤した週の労働時間が週40時間を超えた場合は、その超過分について時間外労働の割増賃金の支払いが必要です 。
- 代休は、休日労働を行った事実が変わらないため、休日労働に対する割増賃金の支払い義務があります 。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。