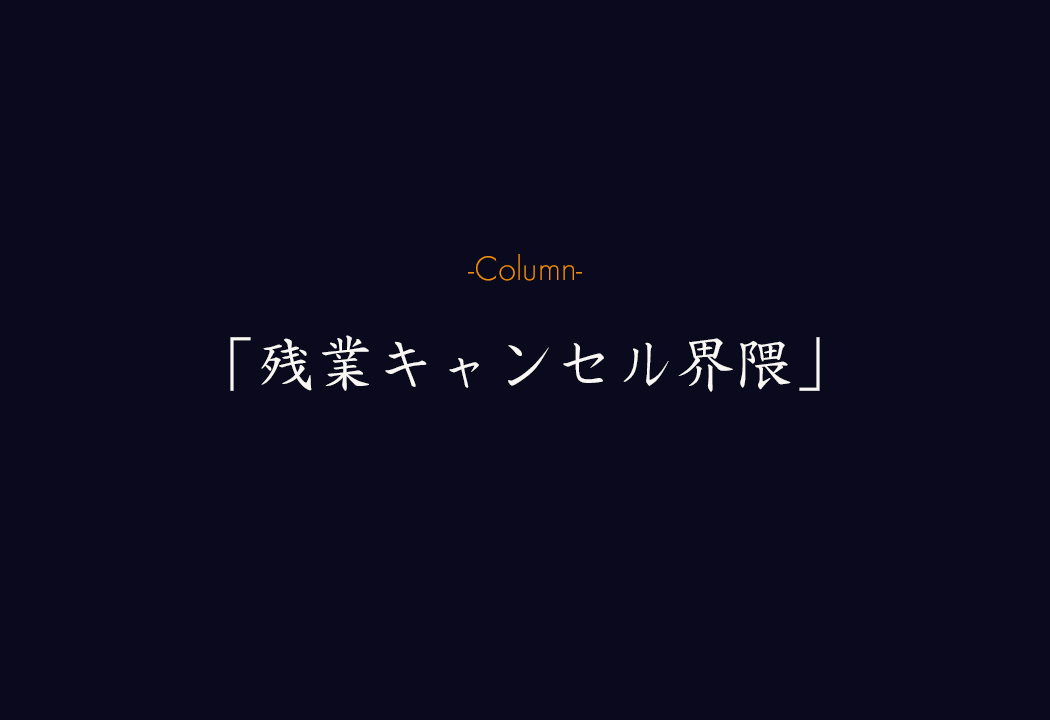【はじめに】
話題の「残業キャンセル界隈」
最近、SNSなどを中心に「残業キャンセル界隈」という言葉が話題になっています。もしも、御社でこのような従業員が現れた場合、会社としてどのように対応すればよいのでしょうか。
本記事では、その具体的な対応方法について解説します。
【まずは結論】
労働者は原則として残業命令に応じる義務がある
結論から申し上げますと、会社は一定の要件を満たせば、労働者に残業を命じることが可能です。そして、労働者は原則としてその命令に応じる義務があります。
正当な理由なく残業命令を拒否し続ける従業員に対しては、懲戒処分や、最終的には解雇といった厳しい対応も、判例上有効と判断されるケースがあります。
【解説します】
1. 実は昔から存在した「残業キャンセル界隈」
「残業キャンセル界隈」という言葉が生まれる以前から、残業を拒否する従業員というのは、どの職場にも一定数存在し、会社にとって問題の種となっていました。 労働契約を結ぶということは、労働者は使用者の指揮命令下で労働力を提供する義務を負い、使用者はその対価として賃金を支払う義務を負う、という関係に立つことをまず理解しておく必要があります。
2. 残業命令は可能か? – 最高裁判所の判断
この点について、参考となる重要な判例があります。 仕事上のミスについて上司から残業してやり直すよう命じられたものの、これを拒否し、その後の説得にも反抗的な態度をとり続けた従業員がいました。
会社は出勤停止の懲戒処分を行いましたが、それでも従業員が態度を改めなかったため、最終的に懲戒解雇としました。
このケースについて、裁判所は懲戒解雇を有効と判断しました。
(平成3.11.28 最高裁第一小法廷判決 日立製作所武蔵工場事件)
この最高裁判決以降、適法な要件を満たした残業命令を従業員が正当な理由なく拒否した場合には、懲戒処分や解雇も原則として適法と判断されるようになり、残業命令についても個々の従業員の同意までは必要ないと解されています。
3. 残業命令を「適法」にするための要件
ただし、会社が従業員に残業を命じるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 事業場で、時間外労働・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)が適正に締結され、所轄の労働基準監督署長へ届け出られているか
- 命令する残業の理由が、36協定に記載されている「時間外労働をさせる必要のある具体的な事由」と一致しているか
- 命令する残業の時間が、36協定で定めた延長時間の上限の範囲内か
- 労働契約書や就業規則等で「業務上の必要がある場合には、時間外労働を命じることがある」旨が記載されているか
これらの要件を満たして初めて、残業命令は法的な効力を持つことになります。
4. 残業を拒否された場合の具体的な進め方
上記の要件を満たしているにもかかわらず、従業員に残業を拒否された場合は、以下の手順で対応を進めることが考えられます。
- ①まずは話し合い、残業できない理由を確認し、説得する
はじめに、なぜ残業ができないのか理由を確認します。それが正当な理由でなければ、残業が必要な業務上の理由を丁寧に説明し、命令に応じるよう説得することが第一歩となります。 - ②説得に応じないときは、残業命令を文書で出す
それでも従業員が従わない場合、その指示が単なる「お願い」ではなく、会社の正式な「業務命令」であることを明確に伝える必要があります。口頭での指示だけでは後に「言った、言わない」という問題になりかねませんので、メールや業務命令書といった文書で記録に残すことが重要です。 - ③それでも残業命令に従わないときは、懲戒処分を検討する
文書による明確な業務命令にも従わない場合、その従業員を放置することはできません。残業命令に応じている他の従業員に対して示しがつかないだけでなく、他にも同様の従業員が現れ、職場全体の秩序が乱れる危険性があるためです。就業規則の懲戒規定に基づき、譴責(けんせき)や減給といった懲戒処分を検討します。 - ④懲戒処分をしても改善されず、やむを得ないときは解雇を検討する
①から③までの手順を踏み、会社として手を尽くしたにもかかわらず、従業員の態度に改善が見られない場合、最終的な手段として解雇を検討することになります。前述の日立製作所武蔵工場事件においても、度重なる命令拒否の末の懲戒解雇は有効と判断されています。
【まとめ】
ポイントの整理
- 労働者は、会社が要件を満たして発した残業命令には、原則として従う義務があります。
- 会社が残業を命じるには「36協定の締結・届出」や「就業規則等への明記」などが不可欠です。
- 従業員から残業拒否の申し出があった場合は、まず理由を確認し、対話による説得を試みることが重要です。
- 正当な理由なく業務命令に従わない場合は、放置せず、懲戒処分など毅然とした対応を検討することが求められます。
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。