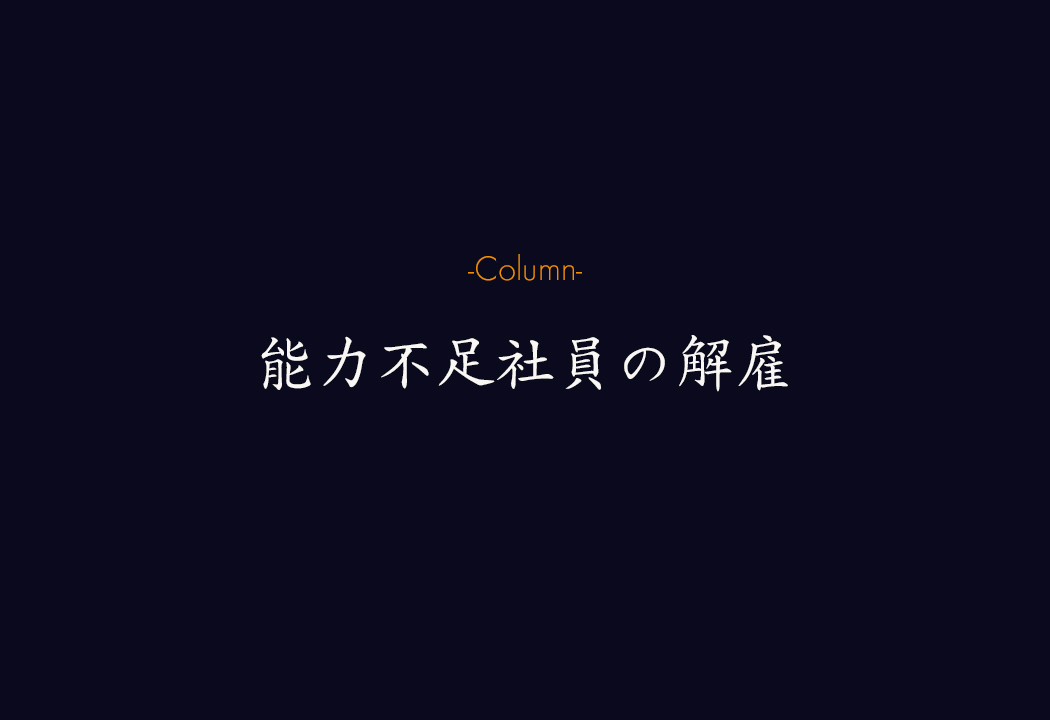【はじめに】
「期待したパフォーマンスを全く発揮してくれない社員がいる」
「何度指導しても改善が見られないが、どう対応すればよいのか」
多くの経営者や人事担当者の方にとって、従業員の能力不足は深刻な悩みの一つではないでしょうか。
しかし、早計な判断で解雇という手段に踏み切ることは、大きなリスクを伴います。
最悪の場合、「不当解雇」として法的な紛争に発展し、企業イメージの低下や金銭的な負担につながる可能性も少なくありません。
この投稿では、従業員の能力不足という問題に直面した際に、法的な紛争リスクを避け、適切に対応するための具体的な手順と留意点を解説します。
【まずは結論】
はじめに最も重要な点をお伝えします。
それは、「能力不足のみを理由に、即時に従業員を解雇することは法的に極めて困難である」ということです。
日本の労働法では、解雇はあくまで最終手段と位置づけられています。
解雇を選択する前に、会社として「改善のための具体的な指導」や「他の職務への配置転換の検討」といった、解雇を回避するための努力を尽くすことが求められます。
これらの手順を真摯に実行してもなお改善が見られず、業務に支障が生じている場合に、初めて「退職勧奨」や、最終手段としての「普通解雇」が視野に入ってくるとご理解ください。
【解説】
能力不足による解雇が法的に難しい理由
なぜ、能力不足を理由とする解雇は慎重な対応が求められるのでしょうか。それは、労働契約法という法律に、解雇に関する重要なルールが定められているからです。まずはその条文をご確認ください。
(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
この条文にある通り、労働者の立場は法律で保護されており、会社が自由に従業員を解雇できるわけではありません。
このルールの背景には、日本の社会に根付いてきた独特の雇用慣行が大きく影響していると考えられます。
多くの日本の企業では、長年にわたり、入社から定年まで一つの会社で勤め上げる「終身雇用」が一般的でした。
この安定した雇用の保障と引き換えに、労働者は会社からの広範な人事権を受け入れてきた側面があります。
例えば、本人の意に沿わない部署異動や、家族を伴う転勤といった大きな変化も、雇用が維持されることを前提に受け入れてきました。
このように、長期的な雇用を前提として労働者が会社に尽くす一方で、会社側にも簡単には労働者を解雇せず、雇用を守るべきであるという考え方が、社会的な共通認識として醸成されてきたのです。
裁判所が解雇の有効性を判断する際にも、こうした背景は前提となっています。
そのため、会社が教育や配置転換といった手段を尽くして解雇を回避する努力をしたかどうかが問われます。
条文にある「客観的に合理的な理由」や「社会通念上の相当性」という言葉の裏には、こうした日本の雇用社会における歴史的な背景がある、とご理解いただくと分かりやすいかと存じます。
ケース1:雇い入れて間もない社員(試用期間中など)への対応ステップ
「試用期間は“お試し期間”だから、能力が低ければ自由に本採用を拒否できる」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは法的には正しくありません。試用期間中の解雇や、期間満了後の本採用拒否も、法的には「解雇」とほぼ同様に扱われ、客観的・合理的な理由が求められます。
- ステップ1:改善指導の実施とプロセスの「記録化」
何よりもまず、具体的な改善指導を行うことが全てのスタート地点です。そして、後々のトラブルを防ぐために最も重要なのが、指導のプロセスを客観的な形で「記録」として残すことです。
指導の責任者を定め、「いつ、誰が、どのような問題点について、どう具体的に指導したか」を記録するようにしましょう。
本人には業務日報を書かせ、指導の内容きちんと理解できているかを確認します。
指導の際、人格を否定するような言動はパワーハラスメントにあたる可能性があるため、あくまで問題となっている業務上の行動に絞って具体的に伝えることが肝心です。 - ステップ2:改善期間の設定と明確な目標提示
一定の指導を行った後は、改善のための期間を明確に設けます。
その上で、定期的に面談(月に1〜2回が目安)を行い、改善の進捗を確認し、フィードバックを続けます。 - ステップ3:他の職務への適性の検討
現在の仕事が本人の適性に合っていない可能性も考えられます。
他の部署や異なる業務であれば能力を発揮できるかもしれないため、転換が可能な部署や業務があるのであれば、配置転換が可能かどうかを検討することも、会社が果たすべき「解雇回避努力」の一環と見なされます。 - ステップ4:最終的な処遇の決定と解雇予告
これらの手順をすべて尽くしてもなお改善が見られず、業務に支障をきたす状態が続く場合に、最終的な選択肢として本採用の拒否や解雇を検討します。
その際には、原則として30日以上前に解雇することを本人に伝える「解雇予告」を行うか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法第20条)。
(※注)ただし、試みの使用期間中の者であって、雇入れの日から14日以内に解雇する場合は、この解雇予告の手続きは不要とされています(労働基準法第21条)。
ケース2:長年勤めた社員への対応ステップ
長年にわたり勤務してきた社員の場合、その能力でこれまで雇用を継続してきたという事実があるため、能力不足を理由とした解雇は、新入社員のケースよりもさらにハードルが高くなります。
- ステップ1:客観的評価に基づく「現状認識」の共有
多くの場合、ご本人は自身の能力に問題があるとは認識していません。
まずは、公正な人事評価制度などを通じて、会社が求める水準と現状との間にギャップがあるという事実を、客観的な評価結果として具体的にフィードバックし、認識を共有することが第一歩です。 - ステップ2:再教育や配置転換による改善機会の提供
ケース1で紹介した改善指導に加え、長年の会社への貢献に配慮し、会社として最大限の改善機会を提供することが重要です。研修プログラムを用意したり、本人の経験や知識が活かせる別の部署への配置転換を打診したりといったアプローチが考えられます。 - ステップ3:役職の見直し(降格)の検討
役職者としての職責を果たせていないと客観的に判断される場合は、人事権の範囲内において役職を解き、能力に見合った職務等級へ変更(降格)することも一つの方法です。これにより、給与水準を職務内容に見合ったものに是正することが可能となります。 - ステップ4:最終的な処遇の決定
会社として考えうるあらゆる手立てを尽くしても状況が改善されず、就業規則に定める解雇事由に該当するような状態が続く場合に、最後の選択肢として普通解雇が視野に入ります。ただし、その判断は極めて慎重に行う必要があります。
解雇の前に検討すべき「退職勧奨」という選択肢
これまで見てきたように、能力不足による解雇は法的なハードルが非常に高く、リスクを伴います。そこで、解雇という強硬な手段に踏み切る前に検討すべきアプローチが「退職勧奨」です。
これは、会社から従業員に対して退職を勧め、双方の話し合いと合意に基づいて雇用契約を終了させる方法です。
例えば、再就職を支援するための一定額の金銭(給与の数ヶ月分など)の支払いなどを条件に、合意退職を提案します。
退職勧奨の場合、失業保険の給付においては「会社都合退職」となり、従業員にとって支給日数が増えるなど有利に取り扱われます。
なお、会社都合退職の扱いとなっても、それによって会社の金銭的な負担が発生することはありません。
ただし、会社が雇用関係の助成金を利用している場合は、一定期間受給ができなくなる等のデメリットが出てくるので注意が必要です。
ただし、この話し合いが「退職強要」になってはいけません。
以下の点は慎んでください。
- 「応じなければ解雇する」といった発言で退職を迫ること。
- 相手が明確に「辞めません」と意思表示しているにもかかわらず、何度も面談を強要したり、長時間にわたり拘束したりすること。
- 仕事を取り上げたり、隔離された場所に席を移したりするなどの嫌がらせ行為を行うこと。
あくまで従業員の自由な意思決定を尊重し、紳士的な話し合いを心がけることが重要です。
【まとめ】
今回は、能力不足の社員への対応について解説しました。重要なポイントを改めて整理します。
- 能力不足を理由とした解雇は、法律で厳しく制限されており、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が問われます。
- 解雇は最終手段です。その前に、改善指導、教育訓練、配置転換など、会社として解雇を回避するための努力を尽くす義務があると考えられています。
- 指導や面談のプロセスは、後々の紛争に備えるためにも、必ず客観的な証拠として「記録」に残してください。
- 試用期間中であっても、本採用の拒否は解雇と同じです。慎重な手続きが求められます。
- 解雇という強硬手段の前に、双方の合意による退職を目指す「退職勧奨」も有効な選択肢ですが、「退職強要」にならないよう細心の注意が必要です。
能力不足の社員への対応は、どの企業にとっても起こりうる難しい問題です。感情的にならず、段階的かつ慎重に手続きを進めることが、会社と従業員の双方にとって最良の解決につながるでしょう。
【参照元】
e-Gov法令検索. (参照 2024-05-16). 労働契約法. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128
e-Gov法令検索. (参照 2024-05-16). 労働基準法. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。