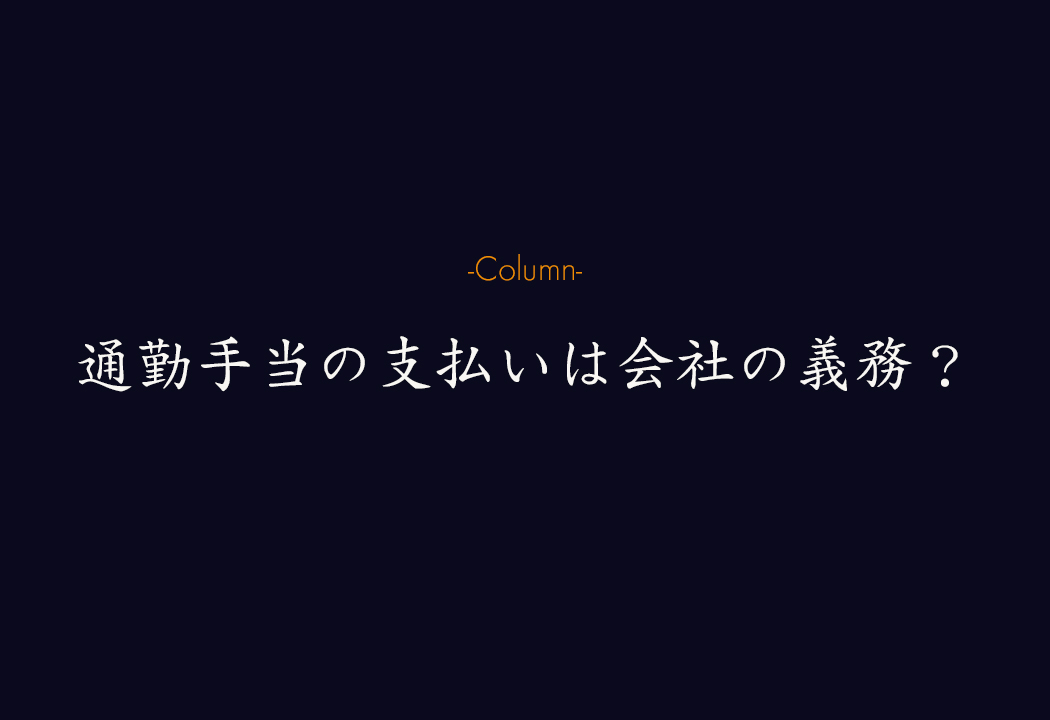通勤手当の支払いは会社の義務?法律の原則を解説します
多くの会社で当たり前のように支給されている「通勤手当」。厚生労働省の調査によれば、9割以上の企業が何らかの形で通勤手当を支給しています。
そのため、「通勤手当の支払いは、会社の法律上の義務」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、結論から言うと、法律上、会社に通勤手当を支払う義務はありません。
今回は、その根拠と、なぜ多くの会社が手当を支給しているのかについて解説したいと思います。
根拠は民法:「通勤費用は労働者負担」が原則
通勤手当の支払いが義務ではない根拠は、民法に定められています。
労働契約において、労働者は「職場(就業の場所)で労務を提供する」という義務を負っています。民法では、この義務を果たす(弁済する)ためにかかる費用は、原則として義務を負う側が負担すると定められています。
(弁済の費用) 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 (民法第485条)
これを労働契約に当てはめてみましょう。
- 債務者:労務を提供する義務を負っている「労働者」
- 弁済の費用:労務を提供するために必要な費用、つまり「通勤にかかる費用」
したがって、法律の原則に立てば、「通勤にかかる費用は、労働者が負担すべきもの」ということになります 。
これが、会社が通勤手当を支払う法的な義務を負わない直接的な根拠です。
例外:もしも会社都合で通勤費が増えた場合は?
ただし、この民法の条文には続きがあります。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (民法第485条 但し書き)
これを労働契約に当てはめると、
- 債権者:労務の提供を受ける権利を持つ「使用者(会社)」
つまり、会社が事務所を移転させたり、従業員に転勤を命じたりしたことで通勤費用が増加した場合、
その増えた分の費用は会社が負担しなければならない、ということになります 。
なぜ義務ではないのに、多くの会社は支給するのか?
では、なぜ法律上の義務ではないにもかかわらず、9割以上の会社が通勤手当を支給しているのでしょうか。その理由以下のようなものが考えられます。
- 福利厚生・実費弁償のため: 最も一般的な理由で、労働者の通勤にかかる経済的負担を軽減し、生活費を補填する目的です 。
- 人材確保・定着のため: 魅力的な労働条件の一つとして通勤手当を支給し、優秀な人材を採用し、長く働いてもらうための経営上の判断です 。
社会保険料と所得税で異なる通勤手当の扱い
通勤手当を実務で扱う上で、間違いやすいのが、社会保険料と所得税での扱いの違いです。
同じ手当でありながら、それぞれの法律で計算に含めるかどうかのルールが異なります。
社会保険料・労働保険料:【保険料計算の対象になる】
健康保険・厚生年金保険などの社会保険料や、雇用保険料・労災保険料の計算において、通勤手当は
全額が「報酬」や「賃金」として扱われ、保険料計算の対象となります 。
「通勤にかかる実費なのに、なぜ保険料計算の対象になるの?」と疑問に思われるかもしれません。
これは、社会保険制度において、事業主から従業員へ支払われるものは、その名目にかかわらず「労働の対価」として広く捉えられるためです。
イメージとしては、「本来、法律上の支払義務がないものを、会社が任意で上乗せして支払っているため、それも労働の報酬の一部と見なす」というイメージです。
所得税:【原則、非課税】
一方、所得税の計算では、通勤手当は一定の限度額まで「非課税」となり、税金がかかりません 。
これは、通勤にかかる費用は、労働者が利益を得る「所得」ではなく、業務のためにやむを得ず発生する「実費」に近いという考え方に基づいています 。
例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、最も経済的かつ合理的な経路の運賃等に対して、
1ヶ月あたり最大15万円までが非課税となります 。
| 項目 | 社会保険料・労働保険料 | 所得税 |
| 扱い | 算定の対象(報酬・賃金に含まれる) | 非課税(一定の限度額まで) |
| 理由 | 労働の対償として受けるものと広く解釈されるため | 通勤にかかる実費を補填するもので、所得とは性質が異なるため |
| 実務への影響 | 標準報酬月額や雇用保険料の算定基礎に含まれる | 限度額までは課税対象額から除外される |
【重要】就業規則や労働契約で定めれば「支払う義務」が生じる
最後に、もうひとつ重要な注意点を説明します。 ここまで通勤手当は法律上の義務ではないと解説してきましたが、一度、就業規則や労働契約書で「通勤手当を支給する」と定めた場合、それは会社にとって法的な「支払う義務」に変わります。
就業規則などで支給基準が明確に定められた通勤手当は、労働基準法上の「賃金」とみなされるためです 。
したがって、一度ルールとして定めた以上は、会社はそのルールに従って、適切に通勤手当を支払わなければなりません。
この投稿が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。