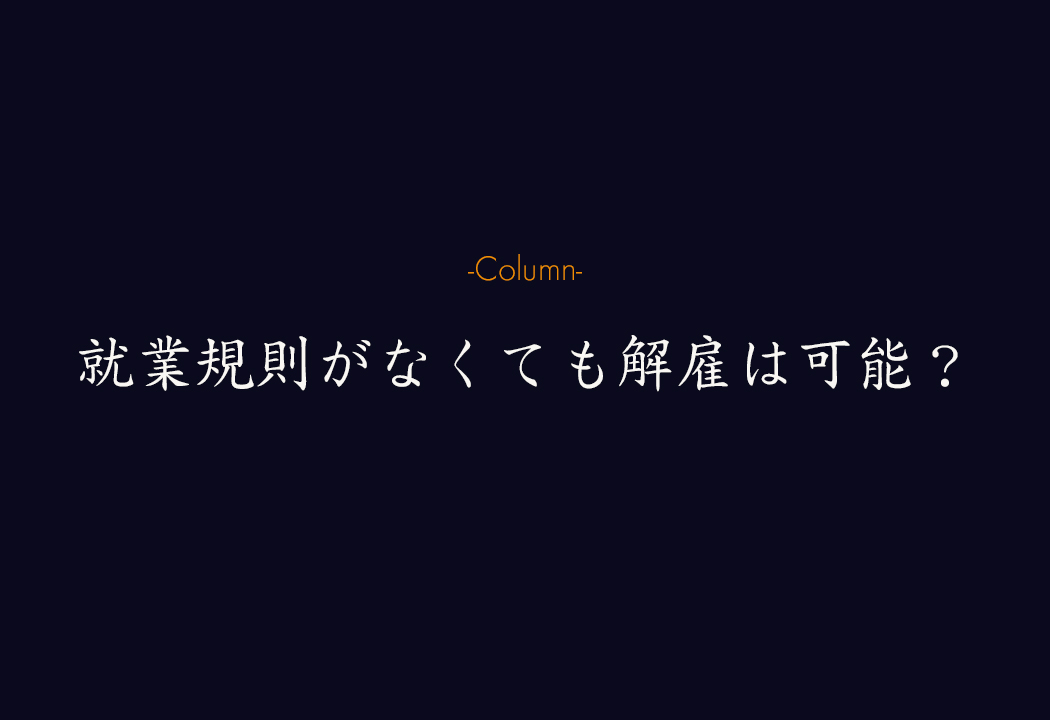就業規則がなくても解雇は可能?「懲戒解雇」との違いとは
日頃、ご相談を受ける中で、「会社に就業規則がないのですが、解雇はできますか?」というご質問をいただくことがあります。
会社のルールブックとも言える就業規則がない状況で、解雇という非常に重い決定がどのように扱われるのか、疑問に感じる方は少なくないでしょう。
この投稿では、「就業規則がないと解雇はできないのか?」という疑問について、特に「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いに焦点を当てながら、分かりやすく解説していきます。
結論:普通解雇は可能、しかし懲戒解雇は就業規則がなければできません
いきなり結論から申し上げると、解雇には種類があり、
- 普通解雇 =就業規則がなくても「可能」です。
- 懲戒解雇(懲罰としての解雇)=就業規則に根拠がなければ「不可能」です。
同じ「解雇」という言葉でも、その性質によって就業規則の要否が異なります。
なぜ「普通解雇」は就業規則がなくてもできるのか?
まず、なぜ普通解雇は可能なのか、その理由から見ていきましょう。
解雇は、使用者(会社側)からの一方的な労働契約の解約の意思表示です。労働契約の成立や終了は、法律上、必ずしも就業規則の存在を前提とはしていません。
そもそも、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられているのは、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」です(労働基準法第89条)。そのため、労働者が10人未満の事業場では、就業規則を作成する義務がないため、就業規則が存在しないケースも決して珍しくはありません。
厳しいルール「解雇権濫用法理」
普通解雇が就業規則なしで可能だとしても、無制限に認められるわけではありません。ここで重要になるのが「解雇権濫用法理(かいこけんらんようほうり)」という考え方です。
これは、労働契約法という法律に明記されています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(労働契約法第16条)
少し難しい言葉が並んでいますが、これは、たとえ使用者に解雇する権利があったとしても、その権利の行使が濫用(やりすぎ)と判断されるような解雇は、法的に無効になるということを意味します。
この条文を分解すると、有効な解雇と認められるためには、次の2つの要素が不可欠であることがわかります。
客観的に合理的な理由があること
これは、誰が聞いても「その理由であれば解雇もやむを得ない」と納得できるような、客観的で正当な理由を指します。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・従業員側に起因する理由:重大な経歴詐称、度重なる無断欠勤、業務命令に対する悪質な違反、職務遂行能力の著しい不足など。
・会社側に起因する理由:経営不振による人員整理(整理解雇)など。ただし、整理解雇が認められるには、さらに厳しい要件があります。
社会通念上相当であること
これは、解雇という処分が、従業員の行為や状況に対して「重すぎないか」というバランスの問題です。例えば、一度の遅刻や比較的軽微なミスでいきなり解雇する、といった処分は、社会の一般的な感覚から見て「相当ではない(やりすぎだ)」と判断される可能性が高いでしょう。
就業規則がない場合、どのような行為が解雇の対象となるのかという基準が不明確なため、「その行為が解雇に値するほどの重大なルール違反であると、従業員が事前に認識できたかどうか=一般的な信頼関係が破壊されたかどうか」を後から使用者が証明することは、就業規則がある場合に比べて難しくなると考えられます。
ただし、「懲戒解雇」は就業規則の根拠が必須です
普通解雇とは別に、「懲戒解雇」という種類の解雇があります。これは、従業員が企業の秩序を著しく乱すような行為(例えば、重大な横領や犯罪行為など)を行った場合に、罰として行われる最も重い懲戒処分です。
この懲戒解雇を行うためには、必ず就業規則にその根拠が必要です。
なぜなら、懲戒処分は会社が従業員に科す「罰」だからです。どのような行為をすれば、どのような罰を受けるのかが、あらかじめルール(就業規則)として定められ、全従業員に周知されていなければ、会社は罰を与えることができないのです。これは「罪刑法定主義」という法律の基本的な考え方に通じます。
したがって、就業規則がない、または就業規則があっても懲戒解雇に関する定めがない会社では、懲戒解雇を行うことはできません。
| 比較項目 | 普通解雇 | 懲戒解雇 |
| 性質・目的 | 労働契約の継続が困難になったことによる契約の終了 | 企業秩序に違反したことに対する「罰」としての処分 |
| 就業規則の要否 | 不要。ただし解雇権濫用法理の制約を受ける。 | 必須。就業規則に懲戒事由と処分の種類が明記されている必要がある。 |
| 典型的な理由 | 能力不足、勤務成績不良、協調性の欠如、経営不振など | 業務上横領、重大なハラスメント、経歴詐称、長期間の無断欠勤など |
| 労働者への影響 | 退職金は規定通り支払われることが多い。 | 退職金が不支給または減額されることが多い。 |
就業規則の有無に関わらない「解雇予告」の義務
最後に、解雇の種類にかかわらず適用されるルールが「解雇予告制度」です。
使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として、
少なくとも30日前にその予告をする必要があります。
もし、この30日前の予告を行わないのであれば、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。例えば、10日前に予告した場合は、差額の20日分以上の解雇予告手当が必要になります。
このルールは、労働者が突然収入を絶たれることなく、次の仕事を探すための時間的・経済的な猶予を与えることを目的としており、就業規則の有無や、それが普通解雇か懲戒解雇かといった種類とは一切関係なく、すべての使用者に適用されます。
※ただし、懲戒解雇の理由が「労働者の責めに帰すべき事由(盗撮や横領など、極めて悪質な非違行為)」に該当する場合で、事前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受ければ、解雇予告や手当なしでの即時解雇が例外的に認められます。
まとめ
今回の内容を整理しましょう。
- 普通解雇は、就業規則がなくても法律上は可能です。
- ただし、全ての解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効となります(労働契約法第16条)。
- 懲戒解雇(罰としての解雇)を行うには、あらかじめ就業規則にその理由と種類が明記されていることが必須です。
- 解雇の種類にかかわらず、原則として30日以上前の予告または解雇予告手当の支払いが義務付けられています(労働基準法第20条)。
結論として、「就業規則がないから解雇は絶対に無効だ」とは一概には言えませんが、「懲戒解雇」については、就業規則がなければ無効となります。
この投稿が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
【参照元】
- e-Gov法令検索. (参照 2024-05-16). 労働契約法. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128
- e-Gov法令検索. (参照 2024-05-16). 労働基準法. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
私で力になれることがあればなんなりとお申し付けください。